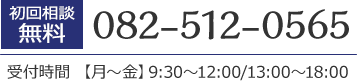従業員が14日以上も無断欠勤を繰り返していて、どう扱えばよいか困っていませんか。自然退職扱いにしたいと考えているかもしれませんが、やり方を間違えると法的にさまざまなリスクが生じる恐れもあります。
この記事では、14日間無断欠勤している従業員を自然退職する方法について紹介します。従業員の問題に悩まされている事業者は、ぜひ参考にしてください。
自然退職とは?
自然退職とは、従業員や企業が意思表示をしなくても、特定の要件を満たしたら自動的に退職の効果が生じることです。会社法や労働基準法で明確に定義されているわけではありませんが、就業規則に定めると退職扱いにできます。
自然退職となる主なケース
自然退職となる例として、主に以下のケースが挙げられます。
- 従業員が定年を迎えた
- 従業員が亡くなった
- 休職期間が明けたものの復職できなかった
- 長期的に無断欠勤を繰り返した
したがって無断欠勤を繰り返した場合でも、自然退職扱いにすることは可能です。
14日間の無断欠勤をすると自然退職になる?
長期的な無断欠勤は自然退職扱いになる可能性がありますが、「14日間」という期間では認められるのでしょうか。ここでは就業規則の内容別に、14日間の無断欠勤をしたときに自然退職扱いできるかどうかを解説します。
就業規則に「無断欠勤14日以上で自然退職」と規定されている場合
就業規則に「無断欠勤14日以上で自然退職」と規定されているときは、問題なく効力が発揮するのが原則です。従業員が14日以上も出社しないとなると、業務が回らなくなる恐れもあります。企業からすれば、無断欠勤をしている従業員を退職扱いにして、新たな人材を確保したいと思うでしょう。
就業規則にきちんと定めているのであれば、仮に訴えられたとしても企業側が有利に働きやすいといえます。自然退職は解雇ではなく退職扱いになるため、基本的に解雇予告手当なども支払う必要はありません。
就業規則に「無断欠勤14日以上で懲戒解雇」と規定されている場合
就業規則に「無断欠勤14日以上で懲戒解雇」と規定されている場合も、その効力が発揮されます。ただし解雇通知の場合、本人に通知が到達していなければなりません。連絡が取れない場合は、裁判所の掲示板や官報に掲載する公示送達の手続きをする必要があります。
裁判所に申し立てたあと、公示送達がなされたら通知は到達したとみなされます。とはいえ申し立てに費用や時間がかかるため、自然退職として処理したほうが手間は省けるでしょう。
就業規則に退職に関する規定がない場合
就業規則に退職に関する規定がないときは、自然退職の処置をとるのが難しくなります。一方で以下の方法を採用すれば、退職させることも不可能ではありません。
- 解約の申し入れがあったとみなす
- 雇用契約終了の意思があったとみなす
民法第627条によると、解約を申し入れた日から2週間経過したら雇用契約を解除したとみなされるためです。とはいえ従業員から退職を断られた場合は、強制的に辞めさせるのは原則できません。
企業が自然退職扱いとする際の手順
企業が従業員を自然退職扱いにするには、基本的に次の手順を踏む必要があります。
- 就業規則の確認
- 従業員への連絡
- 出勤の督促
- 自然退職の通知
- 退職手続きの実施
それぞれのステップごとに、注意すべきポイントをまとめます。
就業規則の確認
まず自然退職の処置をとるには、自社の就業規則を確認しなければなりません。自然退職に関するルールが規定されていなかったら、逆に従業員側から訴えられる恐れがあります。自然退職の規定があった場合でも、弁護士に内容が問題ないかを調べてもらうのが賢明です。
従業員への連絡
自然退職として処理する前に、無断欠勤をしている従業員の状況を確認しなければなりません。連絡を入れる際には電話だけではなく、メールや書面(内容証明郵便など)も活用しましょう。これらの方法を使っても連絡がつかないときは、緊急連絡先または家族とコンタクトを取ってみましょう。
出勤の督促
従業員が一定期間無断欠勤を繰り返しているのであれば、出勤を促す旨の書類を送付しましょう。厚生労働省の方針によると、無断欠勤した事実だけではなく、出勤督促も自然退職が認められるうえで重要な要素となるためです。
督促を出す際には、証拠の残る内容証明郵便を使うのをおすすめします。今後法的トラブルに発展した事態に備え、通知などの記録を細かく残すようにしてください。
自然退職の通知
出勤の督促をしているにもかかわらず、従業員が出勤しないときは自然退職となった旨の通知を送りましょう。通知する際には、基本的に退職届を求める必要はありません。
休職期間満了通知書を従業員に対して送付すれば、トラブルは未然に防ぎやすくなります。当該書面についても、記録が残る内容証明郵便を使うのがおすすめです。
退職手続きの実施
自然退職の通知を送付したあとは、退職手続きを実施しなければなりません。主に必要となるのが、社会保険や雇用保険の手続きです。具体的な方法については後述します。
ほかにも企業で使っているシステムに、自然退職となった従業員の情報を登録している場合は、忘れずに更新しておきましょう。個人情報保護法の観点でも、保管する必要がなくなった個人情報は、削除することが義務づけられています。
企業が自然退職扱いとする際の注意点
企業が従業員を自然退職扱いするときは、主に7つの注意点を守らないといけません。未然にトラブルを防止するポイントにもなるため、どのような点に注意すべきかについて詳しくまとめます。
就業規則を確認する
上述したとおり、自然退職の手続きをとる際には就業規則を確認しなければなりません。ここでポイントとなるのは、「◯日間無断欠勤が継続したら自然退職とする」みたいに明確な基準が記載されているかです。
「長期間」「しばらくの間」などとあいまいな表現を使うと、当該規定が無効とみなされる可能性もあります。
従業員への周知を徹底する
就業規則を定めても、従業員に周知されていなかったら意味がありません。労働基準法にも周知義務について定められており、違反すると罰則が適用される恐れがあります。したがって就業規則を定めたら、従業員への周知を徹底しましょう。
周知する際には口頭だけではなく、書面や社内システムにていつでも共有できるようにすることが大切です。社内システムに保存されていても、パスワードをかけてアクセスできない状態にしてしまうと、周知されたことにはならないので注意してください。
連絡努力を徹底する
自然退職の処置をとる前に、従業員への連絡を欠かしてはいけません。上述したように、電話・メール・書面・緊急連絡先への連絡などと、さまざまな方法を試してください。
ただしこれらの方法を試しても、従業員と連絡がとれないことも考えられます。その際は、書面(内容証明郵便)にて出勤を促すとよいでしょう。
書面には、「応答がない場合は就業規則に基づき自然退職とする」などと記載します。客観的に連絡努力を尽くしたと認められれば、自然退職の手続きがしやすくなります。
記録を保管する
従業員に連絡をしたら、その都度記録を保管してください。ただ漠然と連絡した旨を残すのではなく、以下の項目がわかるようにしなければなりません。
- 日時
- どの職員が
- どのような方法で(電話・メール・書面など)
- 何度連絡をしたか
- 連絡をした結果(通話ができない・返信が来ないなど)
細かく記録を残しておけば、訴訟沙汰に発展しても自社が有利に働きやすくなります。
連絡が取れない理由を考慮する
従業員から応答がない場合、連絡が取れない理由について考慮しましょう。たとえば従業員が事故に巻き込まれたり、病気を抱えたりして連絡できていないのかもしれません。また家庭の事情や精神的な不調といった理由も考えられます。
このような理由があると、自然退職の処置をとることが不当とみなされる可能性があります。まずは従業員全員に対し、無断欠勤している者について何らかの事情を知らないか確認するとよいでしょう。
解雇との混同を避ける
自然退職の手続きをとる際には、解雇と混同しないように注意してください。解雇とは、会社が強制的に従業員を辞めさせる処分のことです。
会社が解雇を下す際には、労働基準法第20条にて30日以上前に解雇予告するか、解雇予告手当(30日以上の平均賃金)を支払わないといけません。このルールを守らないと、6カ月以上の拘禁刑または30万円以下の罰金刑に処される恐れがあります。
自然退職は解雇ではないため、上記のルールを守る必要はありません。しかし解雇とは異なり、強制力は働かないので注意してください。
社会保険・雇用保険の手続きをする
上述したとおり、従業員が退職したら社会保険と雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりません。社会保険では、日本年金機構に「被保険者資格喪失届」を提出します。自然退職が発生してから、年金事務所へ5日以内に手続きしてください。
ほかにもハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、雇用保険の資格喪失手続きをする必要があります。「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する際には、あわせて離職証明書を添付しましょう。
雇用保険の資格喪失手続きにおいては、企業がハローワークから離職票を交付してもらいます。その離職票を退職した従業員に送付し、ハローワークへの提出を促してください。
まとめ
この記事をまとめると、企業が14日間無断欠勤して従業員を自然退職させることは可能です。ただし自然退職の処置をとるには、就業規則を定めているか、従業員に連絡を入れているかなどの要件を満たす必要があります。ほかにも、年金事務所やハローワークで資格喪失手続きをしなければなりません。
これらのステップを踏むうえで、従業員側から訴訟を提起される恐れもあります。こうしたリスクに備え、あらかじめ弁護士に相談しておくとよいでしょう。