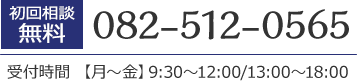運送業を営む会社における法律問題として、典型的に考えられるのは、貨物の輸送に関する契約トラブル、交通事故発生時の対応、人手不足やドライバーの長時間労働からくる労務問題等がありますので、以下、これらについて解説していきます。
・運送契約書等の契約書チェック
運送会社は、顧客との契約に基づいて貨物を輸送していますが、契約違反による法的トラブルが発生しやすい状況にあります。
例えば、契約に納期が定められているとしても、道路状況等により間に合わないことも十分にあり得ますし、運送中に、運送会社の方に過失がなくとも、貨物が損傷したり、紛失したりすることもありえます。また、貨物の取扱い方法や保管条件が契約違反とされることもあります。
一方で、顧客と業者の間で、運送料金の理解が異なって請求額の件でトラブルが発生したり、それが高じて顧客に料金を支払ってもらえないといったトラブルも考えられます。
継続的な取引先との契約においては、サービスの内容、料金体系、支払条件、保険や不可抗力による納期の遅延や貨物の損傷等を定めた基本契約書を作成した上で、個別の取引に関する注文書や契約書を作って発注されるのが一般的と思われますが、この基本契約書については、当事者間に認識の齟齬が生じないよう明確に定めておく必要があります。
また、その契約書が、必ずしも自社にとって有利とはなっていない場合もあり得ますし、以前取り交わした契約書が、現在の実態には合っていないために改定した方が良い場合もあり得るでしょう。
契約書は、上記のようなトラブルの発生を防ぐ効果がありますし、トラブルが発生した場合にも、自社を守る規定を入れておくことが出来ますので、しっかりとした検討が必要です。
契約書の確認については、契約書のページもご覧いただければと思います(★リンク)。
・自動車事故
運送会社においては、日々、車両を運転して貨物を輸送するため、交通事故発生のリスクはつきものです。事故発生時の一般的な対応の流れは以下の様になります。
事故現場の安全確保:事故現場での安全を確保し、けが人がいれば応急処置を行う。交通の妨げにならないように車両を安全な場所に移動する。
警察への通報:事故を警察に通報し、必要なら救急車を呼ぶ。
事故報告書の作成:運転者等において事故の詳細を記録するために、事故報告書を作成する(事故の状況、関係者の情報、目撃証言などをまとめる。)。
保険会社への連絡:保険使用の有無にかかわらず、いったんは事故を保険会社に報告する。保険会社は、必要に応じて、修理見積等必要書類の取得等の指示を行ってくれるので、これに対応する。
被害者との連絡:被害者に保険会社の情報等を開示し、連絡先を交換する。なお、保険会社や弁護士が介入することで、直接は連絡を取らなくて良いこともあります。
示談交渉・訴訟:自身で、あるいは、弁護士を入れるなどして相手方と示談交渉を行い、まとまらなければ裁判を行うこともあります。
なお、運送会社の交通事故には、積荷損害が発生しうるということ、事故による車両損傷によって、車両が使えなくなることで、休車損害が発生しうるという特徴があります。積荷損害については、積荷の評価が難しいという問題があったり、休車損害などは請求するためには一定のハードルがある等、交通事故にも精通した弁護士による対応が求められるでしょう。
賠償:示談、あるいは、訴訟で決められた金額を支払ったり、支払ってもらったりして、事件は解決となります。
この間、当方または先方が、警察に人身事故の届出を提出することもあります。
人身事故の届出を行うことで交通事故が刑事事件とります。
その場合、刑事処分を受ける可能性があるとともに、行政処分の基礎となる点数がつきますので、免許停止や免許取消等の行政処分を受ける可能性があります。
交通事故においては、事故後の初動対応が悪いことが原因となり、解決まで長期間を要することもありますが、早期に弁護士に相談することで、適時に、対応を誤らず、事故処理を進められる可能性が高まるでしょう。
また、顧問弁護士であれば、優先的に相談枠を確保することが可能ですので、問題解決の機会を逸してしまうこともないといえます。
弊所においては、長年損保会社の顧問を務め、交通事故・保険会社対応に精通した弁護士が、事故発生早期の段階で対応を行うことが出来ます。
特に運送会社においては、通常の業種よりも業務中の交通事故発生のリスクは高く、これに備えておくことが必要になりますが、弊所において、顧問契約を締結いただく場合、交通事故発生時において、プランによって上限時間の定めはありますが、面談のほか、電話、チャット、メールでの相談も可能となります。
弊所の顧問弁護士サービスについては、こちらのページをご確認いただければと思います。
また、弊所サイトには交通事故のページもありますので、そちらもご参考ください。
・労務管理
運送会社には特有の労務管理上の問題があります。すなわち、慢性的なドライバー不足から長時間勤務が必要になったり、急なスケジュール変更等により、運転手の過重労働が発生しやすいというものです。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、週に40時間までと規定されており(労働基準法第32条1項)、これを法定労働時間といいます。
そして、いわゆる36協定を締結し、労働基準監督署に届け出て入れていれば、法定労働時間を超過することも認められているのですが、それにも上限があり、原則1か月45時間、1年360時間(1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者については1か月42時間1年320時間)とされています(同法第36条4項)。
臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合であっても、自動車運転の業務については、1年960時間以内としなければなりません(令和6年4月1日から)。
また、自動車運転の業務についても、令和6年4月1日から「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について注意すべき事項等に関する指針」が全面適用されるようになることにも留意する必要があります。
その他、2日平均1日の運転時間や、2週平均1週間の運転時間、連続運転時間に関する規制等、運送会社に特有のルールがあり、とても複雑である上、ドライバーは基本的に会社から離れて仕事をしている以上、労務管理は困難となりがちです。
また、そもそもの人手不足の問題もあり、これらの規制を守ることが物理的に不可能ではないかとも思われる状況でもあり、物流2024年問題などと騒がれています。
とはいえ、長時間労働により、運転手が身体を壊したり、過労による居眠り運転などで事故を起こしたりすれば、労災になる可能性がありますし、会社を辞めてしまうようであれば、その際、未払の残業代をあわせて請求されるリスクもあります。
例えば、次のような考えに基づいて給与計算を行っている場合には、残業代が未払となっている可能性が高いといえるので確認が必要です。
すなわち、①歩合制だから残業代は支払わなくて良いと考えている、②荷待ち時間は労働時間に含まれないとの認識で残業代を支払っていない、③みなし残業代を支払っているためそれを超える残業代を支払う必要がないと考え、残業代を支払っていない場合などです。
運送会社においては、もともと長時間労働が常であるため、全ての未払残業代を請求されるとその額が莫大となることもしばしばです。
辞めた従業員から突然残業代を請求されて焦らないためにも、きちんとした勤怠管理を行う必要があります。
自社の勤怠管理に問題がないか、ご不安をお持ちの運送会社様は、弁護士にご相談いただければと思います。
・問題従業員
運送業は慢性的な人手不足であり、採用にはとても苦労が伴います。このため、採用した人材の中に、一定数、問題社員となり得る人材が含まれてしまう可能性もあります。また、人手不足の環境では、従業員の立場の方が強くなってしまい易いということもあり、従業員が、会社の指導に従わず規律が保たれなかったり、他の従業員とたびたびトラブルを起こすことで職場環境を悪化させたりする、問題従業員にお悩みの業者様も多いと思われます。
このような従業員にはすぐにでも辞めてもらいたいと考えるかも知れませんが、労働法では、従業員の立場が守られているため、簡単に解雇してしまえば、後に解雇無効と判断されるリスクがありますので、あくまでも段階を踏んで、手続きを行っていくことが重要です。
問題従業員への退職勧奨等には、慎重な対応が求められますので、実際に進める場合には、顧問弁護士等に継続的な相談をしながら行うのが安心でしょう。
問題従業員への対応を含めた労務問題については、労務問題のページに詳細を記載しておりますので、ご覧ください。